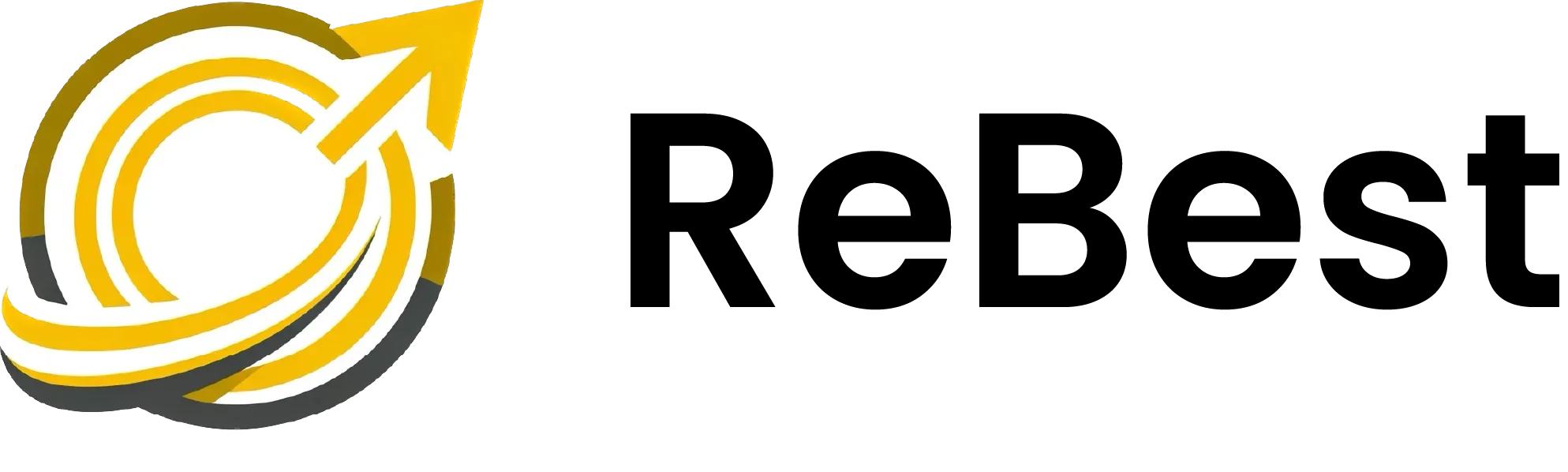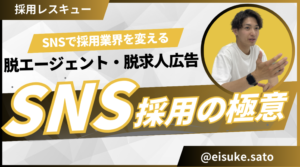【必見】求人広告に頼らず応募が殺到する『SNS採用』の極意!心理学でわかる3つのポイント

【SNS採用の極意とは?】SNS採用支援がもたらす新しい採用のかたち
はじめに
企業にとって「採用活動」は常に大きな課題です。応募が集まらない、人材のミスマッチが続く、ようやく採用しても短期間で辞めてしまう……。こうした問題に頭を悩ませる企業は少なくありません。特に、中小企業やベンチャー企業の場合、大手のように多額の広告費をかけられず、思うように応募が集まらないというケースも多いでしょう。
そんな状況を打破するために、いま注目されているのが「SNS採用」です。本記事では、YouTubeチャンネル「【SNS採用の極意とは!?】SNS採用支援を徹底解説!」で語った内容をもとに、SNS採用の特徴やメリット、そしてどのように活用すれば理想的な人材獲得につながるのかを詳しくご紹介します。
1. 従来の採用手法が抱える課題
1-1. 求人広告やエージェントへの依存
一般的に求人を行う際、求人広告や転職エージェントなどを利用する企業が多いのではないでしょうか。しかしこの方法は、広告枠を大きく確保できる大手企業が有利になりやすいという構造的な問題を抱えています。広告枠を買うための費用を潤沢に出せる企業ほど、多くの求職者の目に留まる機会が増え、中小企業やベンチャー企業は埋もれてしまいがちです。
1-2. 認知不足による機会損失
企業がいくら魅力的なサービスやビジョン、経営者の想いを持っていても、そもそも求職者に知られていなければ意味がありません。認知不足のままでは、せっかく良い環境を提供している中小企業やベンチャー企業でも応募が集まらない。これは企業にとって大きな機会損失です。
1-3. 入社後のギャップによる定着率の低下
ようやく採用までこぎつけても、その後すぐに退職してしまう人がいる――。こうしたミスマッチの原因の一つは、入社前と入社後の「ギャップ」です。求職者は求人広告の条件や、面接時に聞いた情報だけで入社を決めることが多いため、リアルな社風や具体的な業務内容をイメージしきれません。結果として、「想像と違った」という理由で離職してしまうケースが後を絶たないのです。
2. SNS採用がもたらす新しい可能性

2-1. 脱エージェント、脱求人広告への第一歩
SNS採用は「脱エージェント」「脱求人広告」の採用を目指す企業にとって、有力な選択肢となります。自社のSNSアカウントを通じてダイレクトに求職者へ情報発信を行うため、外部の媒体に大きなコストを払う必要が軽減されます。さらに、SNSが普及した現代では、個人が情報発信の主体となりうる時代です。企業自身が「影響力」を得られれば、よりフラットで透明性の高い採用活動を実現することができるでしょう。
2-2. 認知獲得から定着率向上までワンストップでサポート
SNS採用の特徴は、ただ「応募を集めるだけ」では終わらない点にあります。日々の投稿を通じて、社内の雰囲気や経営者の考え方、働く社員の声などを積極的に発信していくことで、求職者とのコミュニケーションが深まります。これが、内定承諾率アップや入社後の定着率向上にもつながるのです。
たとえば、インタビュー形式で社員の働く様子やキャリアパスを紹介したり、社内イベントや朝礼風景などの動画を発信したりと、SNSを使えばさまざまな形で企業の“リアル”を伝えられます。こうしてギャップを少なくしながら入社を迎えれば、企業と求職者の相互理解が深まった状態となり、早期離職も減らすことが可能です。
3. 採用を左右する重要な3つのステップ
動画の中では、採用を成功させるために大きく3つのポイントがあると語られています。
- 認知(Awareness)
- 採用(Recruiting)
- 定着(Retention)

この3ステップを漏れなく実践することが、採用課題を大きく改善するカギになります。
3-1. 認知(Awareness)
SNSを通じてまず行うべきは、「自社が存在している」「こんな魅力がある」ということを世の中に知ってもらうことです。転職意欲が高い“顕在層”だけでなく、「今すぐに転職したいわけではないが、良い情報があれば興味を持つかもしれない」という“潜在層”にもリーチできるのがSNSの強みです。
潜在層へのアプローチ
転職者の意欲は0〜10段階で表される、と動画の中で解説がありました。これまでの求人媒体は、転職意欲が7〜8以上の“顕在層”をメインターゲットにしています。一方、SNSは転職意欲1〜6の潜在層にも自然に情報を届けることができ、結果として母数を大幅に増やす可能性を秘めています。
3-2. 採用(Recruiting)
認知が広がり、多くの求職者に企業名や事業内容を知ってもらえたら、いよいよ採用に向けた動きを本格化させます。SNS上では、募集要項や実際にどんな職務を担当してもらうかといった情報はもちろん、そこに携わる社員やチームの声を載せると効果的です。書面だけの条件よりも、リアルな「人」の魅力を伝えることで、応募者は“働くイメージ”を持ちやすくなります。
SNS投稿の具体例
- 社内メンバーのインタビュー動画の発信
- 1日の業務スケジュールを短い動画や画像で紹介
- オフィスの様子やイベントの写真を公開
- 経営者の想いやビジョンを語るライブ配信
こうしたコンテンツを通じて、応募前から企業の空気感や社員のリアルな表情を伝えられると、求職者の「ここで働いてみたい」という思いを育てることができます。
3-3. 定着(Retention)
採用が成功しても、そこで終わりではありません。新しく入社した社員が長く活躍し、成長できる環境を整えることが大切です。動画で強調されていたように、SNS発信には「入社前後のギャップ」を小さくする効果があります。
入社後のミスマッチが起きがちな企業や職種ほど、積極的な情報公開が有効です。たとえば、社内のコミュニケーション方法、チームビルディングの取り組み、メンバーが普段どんなモチベーションで働いているのかなど、「小さな日常」を見せることで、転職者の不安を払拭しやすくなります。
4. SNS採用がフラットな採用市場を作る
動画内では「企業と求職者がよりフラットにつながる世界」を作りたい、という想いが語られていました。最近では、フリマアプリやカーシェアなど、個人と個人がダイレクトにつながるプラットフォームが拡大しています。一方、採用の場では、依然として求人広告やエージェントといった“中間業者”に大きな費用をかけ、彼らの影響力に頼らざるを得ない企業が多いのが現状です。
SNS採用によって企業が自らメディアを育て、求職者とダイレクトにつながる仕組みを作れるようになれば、中小企業やベンチャーにも十分なチャンスが生まれます。企業がその魅力を直接アピールし、求職者が自分の目で企業を選べる――。それこそが「フラット」な採用市場の第一歩となるのです。
5. 中小企業にこそSNS採用が必要な理由
5-1. 大手企業との広告費競争に巻き込まれない
前述の通り、大手企業は莫大な広告予算を投じることができ、求人サイト上で存在感を放つのは容易です。一方で、中小企業は少ない予算で採用活動を行うことがほとんど。そこで、無理に広告枠を買おうとするのではなく、SNS上で自社アカウントを運用し、コツコツと認知度を高めていくほうが得策と言えます。
5-2. 社長や社員自身が「メディア」となる
企業の規模が小さいほど、トップの魅力や現場メンバーの人柄が、そのまま企業の個性や強みに直結します。これを生かすためにも、代表や社員が積極的にSNSで発信していくことが不可欠。SNSは「人」を見せるツールとして非常に優秀です。社長がビジョンや価値観を語り、社員が普段どのように働いているかを見せることで、「この会社ならでは」の魅力が自然に伝わります。
5-3. 潜在層へのリーチによる母集団形成
先にも触れた通り、転職意欲がそこまで高くない人でも、魅力的な情報があれば「ちょっと考えてみたい」と心が動くかもしれません。特に中小企業の多くは、ターゲットにしている職種や採用したい人材の幅が狭いケースが多いため、「今すぐにでも転職したい人」を待っているだけでは限界があります。潜在層へのアプローチが可能なSNSは、将来の求職者候補を増やす手段として大きな効果を発揮します。

6. 具体的な成功事例:SNS採用で中小企業がエンジニア採用を達成
動画の中で語られていた事例として、15名以下の中小企業がSNS採用を活用してエンジニアの経験者を採用できたというお話がありました。その企業は、社長や会社としての魅力は大きいにもかかわらず、求人広告を出す予算を多く割けず、従来の採用手法では応募が集まらない状況に陥っていました。
そこで、Twitter(現:X)などのSNSアカウントを活用し、社員や社長の生の声、エンジニアがどんな業務をしているかを継続的に発信していった結果、3ヶ月で理想の人材を採用できたのです。これは、「企業がきちんと情報発信を続ければ、求職者がその情報をキャッチしてくれる」ことを示す好例と言えます。
7. SNS採用を成功させるポイント
7-1. 継続的な情報発信が命
SNSを始めたばかりの頃は、フォロワー数やいいね数が少なくても焦る必要はありません。重要なのは、自分たちの企業らしさを継続して発信し続けること。コツコツと投稿し、興味を持ってくれた人とのやり取りを大切にすることで、徐々にファンやフォロワーが増え、情報が拡散していきます。
7-2. 「中の人」を見せる工夫
SNSで好まれるのは「リアルな声」です。企業の公式アカウントだからといって、無機質な広報文ばかり投稿していては注目を集めにくいのが現実。特にTwitterやInstagramでは、社員の個性、オフィスの日常、業務の裏側など、ちょっとした“人間味”を感じさせる内容が大切です。
7-3. 企業と求職者が対等になれる場を作る
SNSは、企業と求職者がコメント欄やDMを通じて直接コミュニケーションをとれる場でもあります。興味を持った求職者と早い段階で意見交換をしたり、不明点を解消したりすることで、面接前から相互理解が深まり、内定承諾や入社後の定着につながる確率も高まります。
8. まとめと今後の展望
SNS採用は、求人広告や転職エージェントに依存しがちな企業の採用活動に、新しい風を吹き込む手法です。特に以下のようなポイントを意識することで、より効果的な採用活動が期待できます。
- 潜在層へのアプローチ
- 入社前後の情報ギャップを埋める
- 企業のリアルな魅力を発信してブランド力を高める
採用が「企業と求職者が対等な立場で出会い、納得感を持って互いを選び合う」場として機能するためには、企業側の積極的かつ継続的な情報発信が不可欠です。SNSをうまく活用すれば、まだ見ぬ求職者との接点を広げ、これまで埋もれてきた中小企業やベンチャー企業の魅力を届けることができます。
動画内でも語られていたように、今後はSNSを採用だけでなく、社内の文化づくりや顧客への発信にも活かす動きがさらに加速するでしょう。SNSは「広告枠を買うための手段」ではなく、「人と人が直接つながるためのプラットフォーム」。この点を理解し、日々の投稿やコミュニケーションに力を入れることで、脱エージェント・脱求人広告の新しい採用のかたちが確立していくのではないでしょうか。